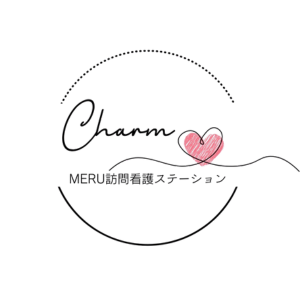代表メッセージ
生い立ち
私は和歌山県出身です。
幼少期は男兄弟に挟まれて、毎日戦いに明け暮れるような遊びをしていました。周囲からは、「兄弟の中で最も男らしく育ったね」などと言われることもあるぐらい、活発に過ごしていたと思います。
遊具の高いところから飛び降りて捻挫したり、頭から滑り台を滑ってすりむいたり、あまりに怪我が絶えないため、母親も少し呆れていたと思います。
そんな私ですが、小学生の頃、小児喘息で病院に行くことが多くなりました。
そこで優しくしてくれた看護師さんに興味を惹かれるようになりました。
母も「看護師になったらええやん」と話してくれたこともあり、小学校の卒業文集には、将来看護師になると書きました。
自然と看護師へ
高校生になったときに、改めて進路を考えたときに、私は看護師になると決めました。
そもそも人と関わることが好きで、気がつけば保健委員もやっていて、自然と看護師への道を歩んでいた気がします。
友達は「まるで刑務所にでも入れられた気分(笑)」などと言っていましたが、いろいろと厳しかった看護学校は、同学年で一人も欠けることなく全員で卒業することができました。
晴れて看護師として働き始めることになります。
看護師デビュー
急性期病院で働き始めた頃、新人担当だった先輩から大変厳しく指導いただきました。怖くて仕方がない日々でした。
今でも忘れられないのは、新人で何もわかっていないときのこと。
両腕を怪我されていた患者さんをみていましたが、手先のほうはなんともなかったので、サチュレーションを指に挟んだのですが、その時に患者さんが少し痛そうにされました。
先輩からは「腕を怪我しているのに指に挟むなんて、何をやっているの!」と、それはもう、ものすごく怒られました。
「ああ、やってしまった」と落ち込み、反省したことを覚えています。
・怒られる毎日。
・減っていく同期。
・早口すぎて覚えきれない申し送り(笑)
「毎日大変なことがたくさんあるな!」と思いながらの、新人看護師の日々でした。
ただ、確かに身体のしんどさや、怒られて落ち込むことなど多かったですが、それでも「看護師を辞めよう」と思ったことは一度もありませんでした。
新人担当の先輩は鬼のようにも思えましたが、今思えば理不尽を言うことはなく、正しく教えてくれました。後々には一緒に旅行に来てくださることもあり、今では良い指導をしていただいたと、とても感謝しています。
訪問看護へのきっかけは、とある女の子との出会い
病棟時代に、一人忘れられない患者さんがいました。
精神科の患者さんで、高校生ぐらいの女の子です。
いつもは普通の会話をする健全な高校生でしたが、気持ちの浮き沈みがあって、不安定になると職員一人が付きっきりでいないと抑えきれず、大変なことになってしまいます。
この高校生は、将来理学療法士になりたいという夢を持っていました。
実現できたらいいなと思って心の中で応援していましたが、そんな最中に症状が少し落ち着いたこともあり、退院して家に帰ることになりました。
退院できるのは嬉しいことですが、私は退院後のことが、とても心配な気持ちになりました。
・家に戻った後は大丈夫なのか
・不安定な状態になったとき、一体誰がみてあげるのか
・家族など周囲が上手く支えられるような環境はあるのだろうか
・彼女は、夢に向かって進んでいけるのだろうか
こんなことが、ふとした時に何度も頭によぎり、とても心配な気持ちでした。どう考えても、病院だけではこのような患者さんを支えるのには限界がある、こう思うようになりました。
では、このような患者さんのために自分がやれることは何だろう?
その答えの一つとして、「精神科に特化した訪問看護師」という選択肢が出てきました。
思ったら行動です。
私は生まれ育った和歌山から大阪への転居と共に、訪問看護師としての日々をスタートさせます。
訪問看護師をやってみて感じたこと
訪問看護師の仕事環境は、私にとって、とても良いものでした。
土日祝日を休めたり、夜勤がなかったりすることは、最初は「こんなに休んで本当にいいのかな?」と疑ってしまう自分もいたぐらいです(笑)
看護師としても、病院のときよりもご利用者さま一人ひとりにしっかりと向き合って支えていけるので、私がやりたかった姿に、より近いものがありました。
そのため、日々やりがいを感じ、訪問看護師になって良かったと思っていました。
ただ、楽しくやりがいをもって訪問看護の仕事をすると共に、心の病を持つ人たちを支える環境における、問題点も感じるようになりました。
それは、この業界は「訪問看護業と他のサービスとの連携が希薄である」ということです。
精神科の訪問看護が必要なご利用者様が社会生活に馴染んでいけるようになるために、相談支援事業所や就労支援事業所など、様々な支援サービスがあります。そういったサービスも、訪問看護も、もっと連携して支援できれば、より早く成長していけると思います。
しかし、それぞれのサービスが役割として担っている仕事だけをして、連携できずに終わってしまっていることが多いと、気付くようになりました。
もっと関連する複数の支援サービスが、連携して支えていける方法はないものかと、日々考えました。
とある引きこもりの方の話
これら精神的疾患を持つ方を支える業界の課題を、実感することになる経験がありました。
とある女性から、「私の友達が、社会に馴染めなくて引きこもり状態になっている。その家は母子家庭で、本人も親も、どうしていいかわからないから、そのままになっている。何とか助けてあげたい」
こんな話を聞きました。
詳しく聞くと、そんな状態でありながら精神科の病院にかかることもなければ、誰かに相談することもできていない。
どうすればいいか知らないままに、社会に馴染めず辛い想いをしているようでした。
このことを教えてくれた女性に、次のように言いました。
「そのお母さんに私のことを伝えてみて。良ければ相談にのってあげられるかもしれない。」
すると、そのお母さんからすぐに電話がありました。
とても悩んでおられたのですが、やはり、どこで誰に相談すればいいのかもわからなかったそうです。
そうして相談にのることになりましたが、結果的に、その方は自分に合うクリニックと出会ったことで少しずつ改善していき、その後就労支援事業所に通うようになり、仕事もするようになりました。
少しずつ光を取り戻していく姿に、本人もお母様も喜んでおられ、私も嬉しかったです。
役割だからと訪問看護しか考えていなかったら、本来あるべき支援には、たどり着かなかったと思います。
この頃から、「思い切って自分で訪問看護ステーションを立ち上げ、自分が思い描く支援を、少しずつ実現していきたい」
このように自分の中での考えが定まり、後に、MERU訪問看護ステーションを開業することになりました。
MERU訪問看護ステーションが目指すこと
MERUは、和気あいあいとした、穏やかな雰囲気の訪問看護ステーションです。
日々の訪問看護に一生懸命向き合っていますが、それと共に次のようなことを実現していきたいと考えています。
1.MERU訪問看護ステーションでは、ご利用者様や、そのご家族、医療機関、さまざまな障がい福祉サービスと連携して、症状悪化の早期発見早期対応と、必要なサービスの導入を円滑に進めることで、ご利用者様が安心して生活できるように支援するステーションを目指していきます。
2.『看護とは、できないことをサポートすること』と広く浸透しがちであると思っていますが、MERUでは、『やりたいことをサポートする』ということにも、重きを置いていきたいと思います。
「本当は一人暮らしをしたいけど不安…」
「働きたいけど、仕事が続くか不安…」
このような想いを持つご利用者様の、自分らしさと意志を尊重し、自立に向けて一緒に考えられるようなステーションを目指します。
共に支援環境をつくっていきましょう
今では仲間も増えてきて、実現したいことに、少しずつ向かっていけるようになりました。
少しでもMERU訪問看護ステーションが目指すことに共感いただける方がおられましたら、何らかの形で協力して、共に実現を目指していけたら、とても幸せなことだと考えております。
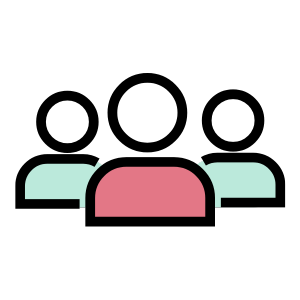
スタッフ紹介
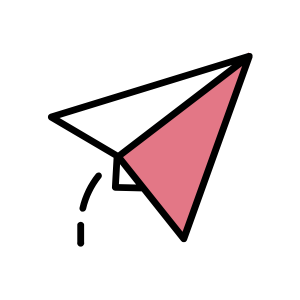
代表メッセージ
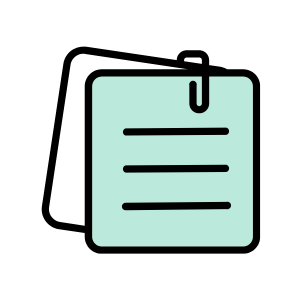
採用情報